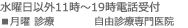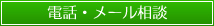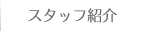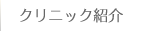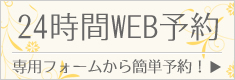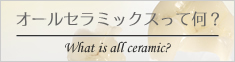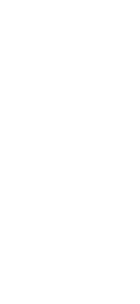毎日何気なく使っている歯ブラシ。店頭に行くと、さまざまな形・硬さ・大きさのものが並んでいて、「どれを選べば良いのか分からない」という声もよく耳にします。また、通常の歯ブラシ以外にも、“タクトブラシ”や“ワンタフトブラシ”といった補助的なブラシも存在し、用途によって使い分けることで、より効果的なセルフケアが可能になります。
このコラムでは、基本的な歯ブラシの選び方から、用途に応じた特殊ブラシの活用法まで、日々のオーラルケアをワンランクアップさせるためのヒントをご紹介します。
歯ブラシ選びの基本:大きさ・毛の硬さ・形状
まず最初に、通常の歯ブラシを選ぶ際のポイントを確認しましょう。
・ヘッドの大きさ
基本的には「自分の親指の第一関節ぐらいの長さ」が目安とされます。大きすぎると奥歯まで届かず、小さすぎると時間がかかるため、自分の口腔内に合ったバランスの良いサイズを選ぶことが大切です。
・毛の硬さ
「やわらかめ」「ふつう」「かため」の3種類が主流です。
・歯ぐきが敏感な人、歯周病の初期段階の人にはやわらかめ
・健康な歯と歯ぐきを持つ人にはふつう
・しっかり磨きたい人にはかため(ただし、力の入れすぎには要注意)
など、口腔の状態によって使い分けが必要です。
・毛先の形状
平らな「フラットタイプ」、山型の「先細タイプ」、ぎっしり詰まった「超密集タイプ」など、ブラシ部分にも様々な設計があります。歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨きたいなら「先細」、歯面をしっかりこすりたいなら「フラット」がおすすめです。
通常の歯ブラシでは届かない場所には“補助ブラシ”を
どれだけ丁寧に磨いていても、歯並びの関係や、歯の形状によって、通常の歯ブラシだけでは清掃が難しい部分が出てきます。そんなときに活躍するのが、補助的なブラシたちです。
・タクトブラシ(歯間ブラシ、ワンタフトブラシ)
いわゆる「ピンポイントブラシ」として、特定の部位を磨くために作られた小さなブラシです。
<タクトブラシ/ワンタフトブラシ>
非常に小さなヘッドと、少し斜めに角度のついたネックが特徴です。
・奥歯の奥(第二大臼歯の遠心面)
・歯並びがガタガタしている部分
・矯正装置の周囲
・親知らずの周辺
など、「通常の歯ブラシでは届きにくい」場所を、ピンポイントで磨くことができます。
ブラシ部分が先細で柔らかいため、歯と歯ぐきの境目に優しく当てることができ、歯周病予防にも非常に効果的です。毎回の歯磨き後に、仕上げとして使用するのがおすすめです。
・歯間ブラシ
歯と歯の間に差し込んで使う、小さなブラシ。特に歯ぐきが下がってきて歯間が広がっている中高年の方や、ブリッジなどの補綴物が入っている方にとっては必須の清掃器具です。
サイズは0番(極細)〜4番(太め)まであり、自分の歯間の大きさに合ったものを選ぶことが重要です。無理に太いものを使うと、歯ぐきを傷つけたり、歯間を広げてしまうリスクがあります。
・電動歯ブラシ
最近では、音波振動式や回転式の電動歯ブラシも人気です。手磨きに比べて一定のリズムで効率よく磨けるのが特長で、正しい使い方をすれば非常に効果的です。ただし、力の入れすぎや長時間の使用には注意が必要で、「電動=何も考えずに磨ける」というわけではありません。むしろ、正しい使い方を理解することが前提となります。
年齢やライフスタイルに応じた歯ブラシの選び方
・乳幼児・小児向け
小さな口に合わせたコンパクトヘッドと、柔らかめの毛が基本です。さらに、子どもが楽しく歯磨きできるように、キャラクター入りや持ちやすい太めの柄など工夫されたものも多く出ています。
・高齢者向け
歯ぐきが痩せてきたり、握力が弱くなった方には、グリップが太く持ちやすい歯ブラシや、やわらかく歯ぐきを傷つけないタイプがおすすめです。また、入れ歯専用のブラシもあり、通常の歯ブラシと併用することで衛生管理がしやすくなります。
・矯正中の方
矯正装置(ブラケットなど)がついている方は、通常の歯ブラシだけでは十分に汚れを落とすのが難しいことがあります。タクトブラシや歯間ブラシ、矯正用のV字カットブラシなどを使って、器具の周囲を丁寧に清掃することが大切です。
「選ぶ+使い分け」で、口腔ケアの質が上がる
歯ブラシは、「1本あればなんとかなる」道具ではありません。毎日のセルフケアにおいては、自分の口腔内の状態やライフスタイルに応じて、“選び”“使い分ける”ことがとても大切です。
たとえば、通常の歯ブラシで全体を磨いたあと、ワンタフトブラシで奥歯の裏側をフォローし、さらに歯間ブラシやデンタルフロスで歯間清掃を行う——これだけでも、プラーク(歯垢)の除去率は大きく変わります。
毎日少しずつでも、正しい道具で正しく磨くことで、歯科医院に頼らなくても自分の歯を守る“本当の意味での予防”が実現できるのです。
まとめ
歯ブラシと一言でいっても、その種類や用途は非常に多岐にわたります。自分の口の状態に合った歯ブラシを選ぶこと、そして必要に応じてタクトブラシや歯間ブラシなどを併用することは、虫歯や歯周病を防ぐための基本です。
「どのブラシを使えば良いのか分からない」「うまく磨けているか不安」という方は、ぜひ歯科医院での歯ブラシ指導を受けてみてください。自分にぴったりの道具と磨き方を知ることは、未来の自分の歯を守る第一歩です。
ご相談 ブランパ梅田院歯科衛生士 岩崎
2025年4月14日 カテゴリ:未分類