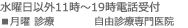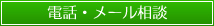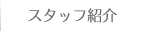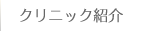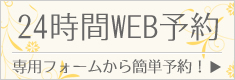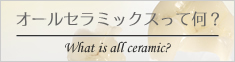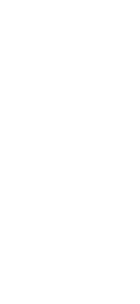近年、医療や介護の現場で「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」という言葉を耳にする機会が増えています。特に高齢者においては、この病気が命に関わる重大なリスクとなることが知られており、実際に日本では肺炎による死亡の多くが誤嚥性肺炎によるものとされています。
では、その予防において「歯科医療」がどのような役割を果たすのか、ご存知でしょうか?「歯医者は虫歯を治す場所」と思われがちですが、実は口腔内の衛生管理や嚥下(えんげ)機能の改善を通じて、誤嚥性肺炎の予防に大きく貢献しています。
本コラムでは、誤嚥性肺炎の概要から、口腔内の環境がどのように肺炎と関係するのか、そして歯科医療が果たすべき役割について詳しく解説していきます。
誤嚥性肺炎とは?~「食べ物の誤飲」だけが原因ではない~
「誤嚥(ごえん)」とは、食べ物や飲み物、あるいは唾液や胃液などが誤って気管に入り、肺に到達してしまうことを言います。通常は、むせたり咳き込んだりすることで排除されますが、加齢や病気により咳反射や嚥下反射が低下していると、気づかないうちに細菌を含んだ物質が肺に入り込み、炎症を起こします。これが「誤嚥性肺炎」です。
特に高齢者では、寝ている間や食後の軽い誤嚥が繰り返される「慢性微小誤嚥(silent aspiration)」が多く見られ、自覚症状がほとんどないまま肺炎が進行することもあります。
なぜ誤嚥で肺炎が起こるのか?~カギは「口の中の細菌」~
口の中には、常に数百種類、数千億個の細菌が生息しています。健康な人であれば問題ありませんが、口腔内の清掃が不十分になると、虫歯菌や歯周病菌をはじめとする病原性の高い細菌が繁殖します。
これらの細菌が唾液や食物に乗って誤って気道に入り込んだとき、肺の中で感染を引き起こすリスクが高まるのです。つまり、**誤嚥性肺炎の本質は「口の中の細菌による肺の感染症」**とも言えます。
したがって、誤嚥性肺炎を予防するためには、単に食べ方や姿勢を工夫するだけでなく、口腔内の清潔さを保つことが極めて重要なのです。
誤嚥性肺炎を引き起こす口腔内の問題とは
1. 歯垢や歯石の蓄積
プラーク(歯垢)は細菌の塊であり、誤嚥時に肺に入ると重篤な肺炎の原因となります。特に歯周病が進行している口腔内では、病原性の高い嫌気性菌が多く存在しており、肺炎の重症化リスクが高まります。
2. 義歯の不衛生
入れ歯の表面には微細な凹凸があり、プラークやカンジダ菌が付着しやすくなっています。夜間も装着したまま寝ていると、唾液の自浄作用も低下し、細菌が増殖しやすくなります。
3. 唾液の減少(口腔乾燥症)
唾液には抗菌作用や自浄作用があり、誤嚥された異物を洗い流す役割も担っています。加齢や薬の副作用、全身疾患によって唾液量が減少すると、感染リスクが増します。
4. 舌苔(ぜったい)や口腔内の汚れ
舌の表面には細菌や食べかすが溜まりやすく、これが口臭や誤嚥性肺炎の原因となります。特に寝たきりの方や要介護者では、舌の清掃が行き届かないケースが多く見受けられます。
歯科治療・口腔ケアが果たす誤嚥性肺炎予防の役割
ここで、歯科の役割が大きく関わってきます。誤嚥性肺炎の予防において、歯科医師や歯科衛生士による専門的な口腔ケアが非常に重要であることが、近年さまざまな研究によって明らかになっています。
1. 定期的な専門的口腔ケア
歯石除去や義歯の清掃、舌苔の除去などを定期的に行うことで、口腔内の細菌数を大幅に減らすことができます。特に高齢者施設や病院での口腔ケアの導入は、誤嚥性肺炎の発症率を下げる効果が示されています。
2. 嚥下機能の評価と訓練(摂食嚥下リハビリ)
歯科医師や歯科衛生士が、嚥下障害の有無をチェックし、必要に応じて「パタカラ体操」や舌の運動、発声訓練などを通じて嚥下機能の改善を図ります。これにより、誤嚥自体を減らすことができます。
3. 口腔機能低下症の早期発見
「オーラルフレイル(口の虚弱)」と呼ばれる初期の機能低下を見逃さず、早期に介入することが、高齢者の全身の健康維持にもつながります。
4. 食形態や食具のアドバイス
歯科から食事の形態(きざみ食、ミキサー食など)や、飲み込みやすい姿勢・補助具の選定などについても指導できるため、日常の誤嚥リスクを下げるサポートが可能です。
誤嚥性肺炎の予防は“チーム医療”で
近年、医科歯科連携の重要性が強調されており、高齢者や在宅療養者に対する医療においては、歯科の介入が欠かせない存在となっています。
たとえば、退院後の在宅療養中に歯科医師が訪問して口腔ケアを行うことで、誤嚥性肺炎の再発を防ぎ、再入院を回避できたというケースも少なくありません。介護職・看護師・医師・栄養士と連携しながら、歯科の視点から口腔衛生と嚥下機能を維持することが、高齢者の「生活の質(QOL)」の向上に大きく寄与します。
高齢者だけではない?誤嚥性肺炎のリスクは誰にでもある
誤嚥性肺炎は高齢者に多い病気ではありますが、若年層であっても、ストレスや疾患、服薬の影響などで唾液が減少したり、体調不良時に寝たまま食事を摂ったりすることで、リスクがゼロとは言えません。
とくに介護や看護の現場では、「まだ若いから大丈夫」と過信せず、日々の口腔ケアを徹底することが大切です。歯磨きやうがいができない人には、保湿剤やスポンジブラシを用いた清掃でも効果があります。
まとめ:歯科治療が「命を守る医療」になる時代
これまで歯科医療は「痛みをとる」「虫歯を治す」といった役割に限られて語られることが多くありました。しかし、今や歯科は「口から始まる全身の健康」を守る重要な医療分野として再評価されています。
誤嚥性肺炎の予防において、口腔の清掃と機能維持は欠かせない要素であり、それを担うのが歯科医師・歯科衛生士の専門的な知識と技術です。日々の口腔ケアが肺炎を防ぎ、命を守る手段となる――それがこれからの歯科の新たな価値です。
家族や大切な人の命を守るために、そして自分自身の老後の健康を守るために、今こそ「口の健康」に目を向ける時です。
2025年4月14日 カテゴリ:未分類